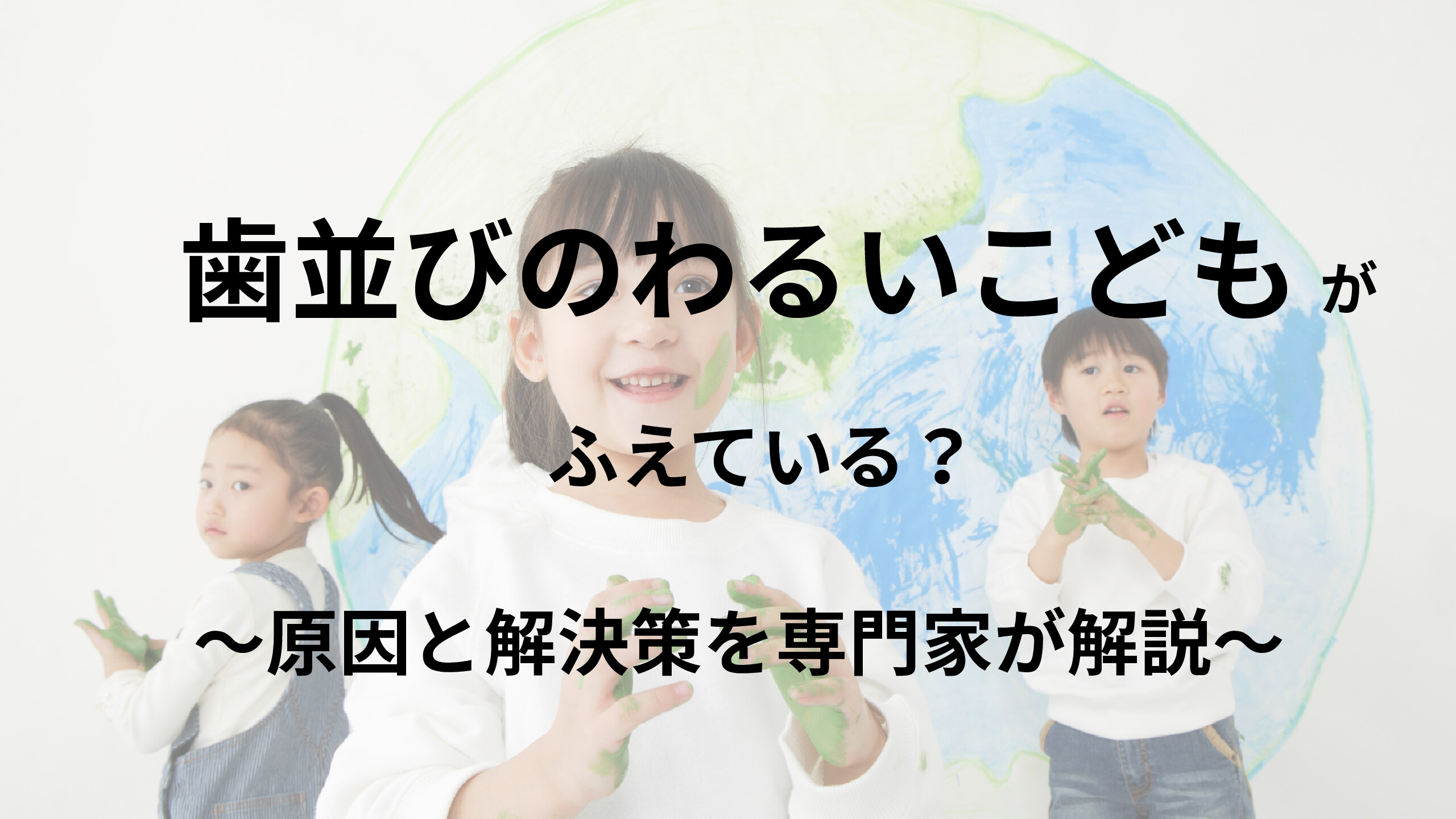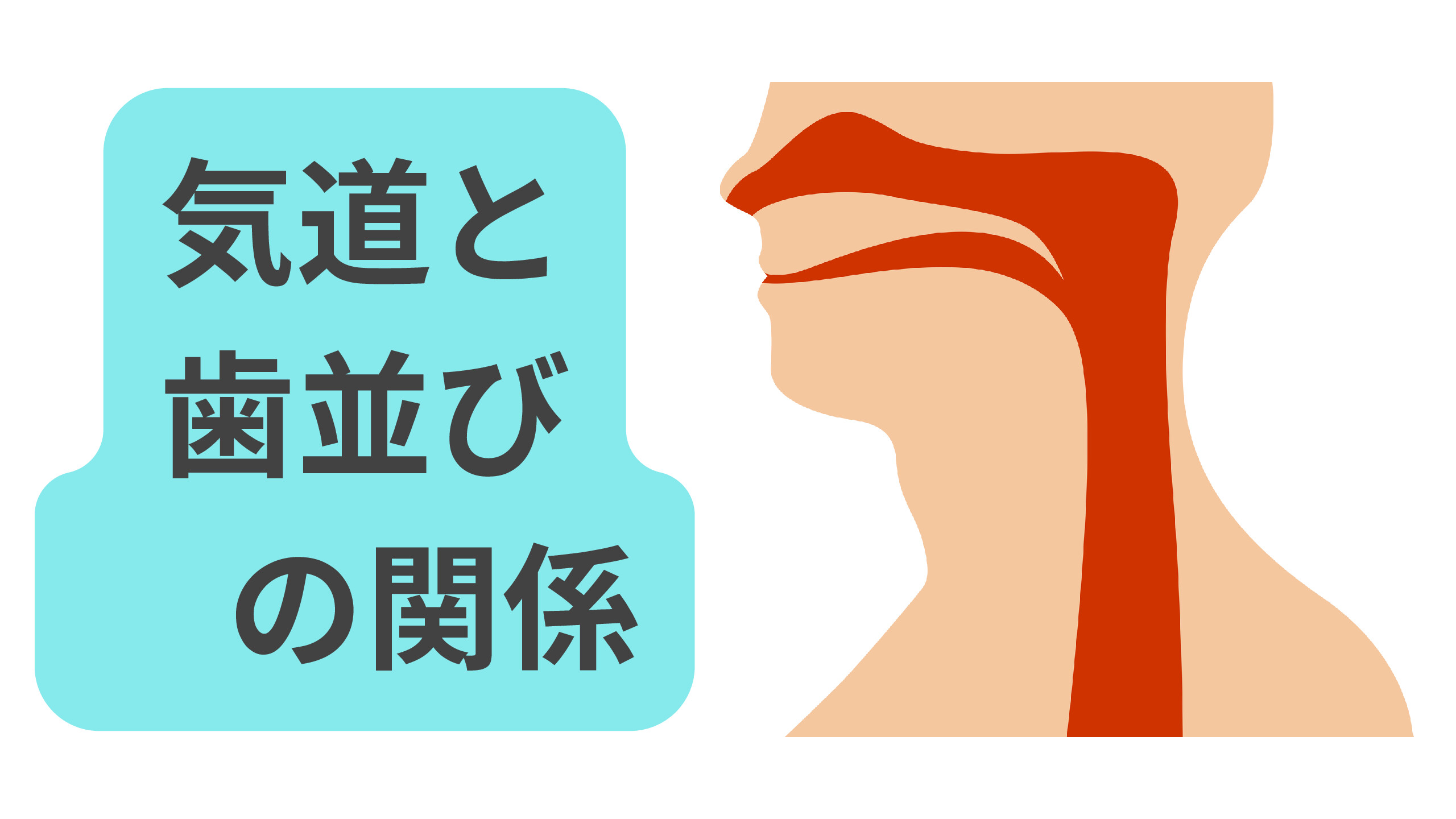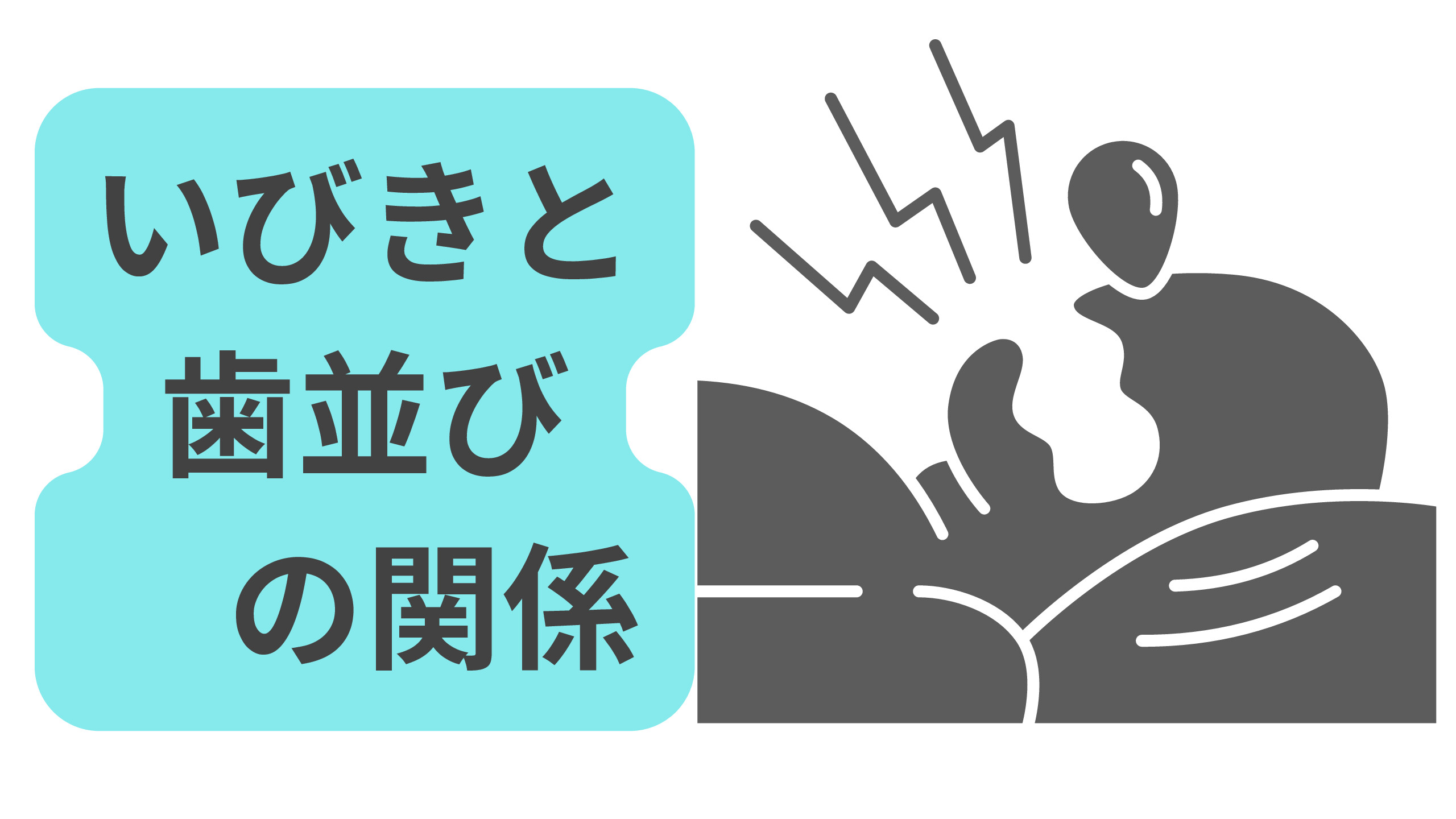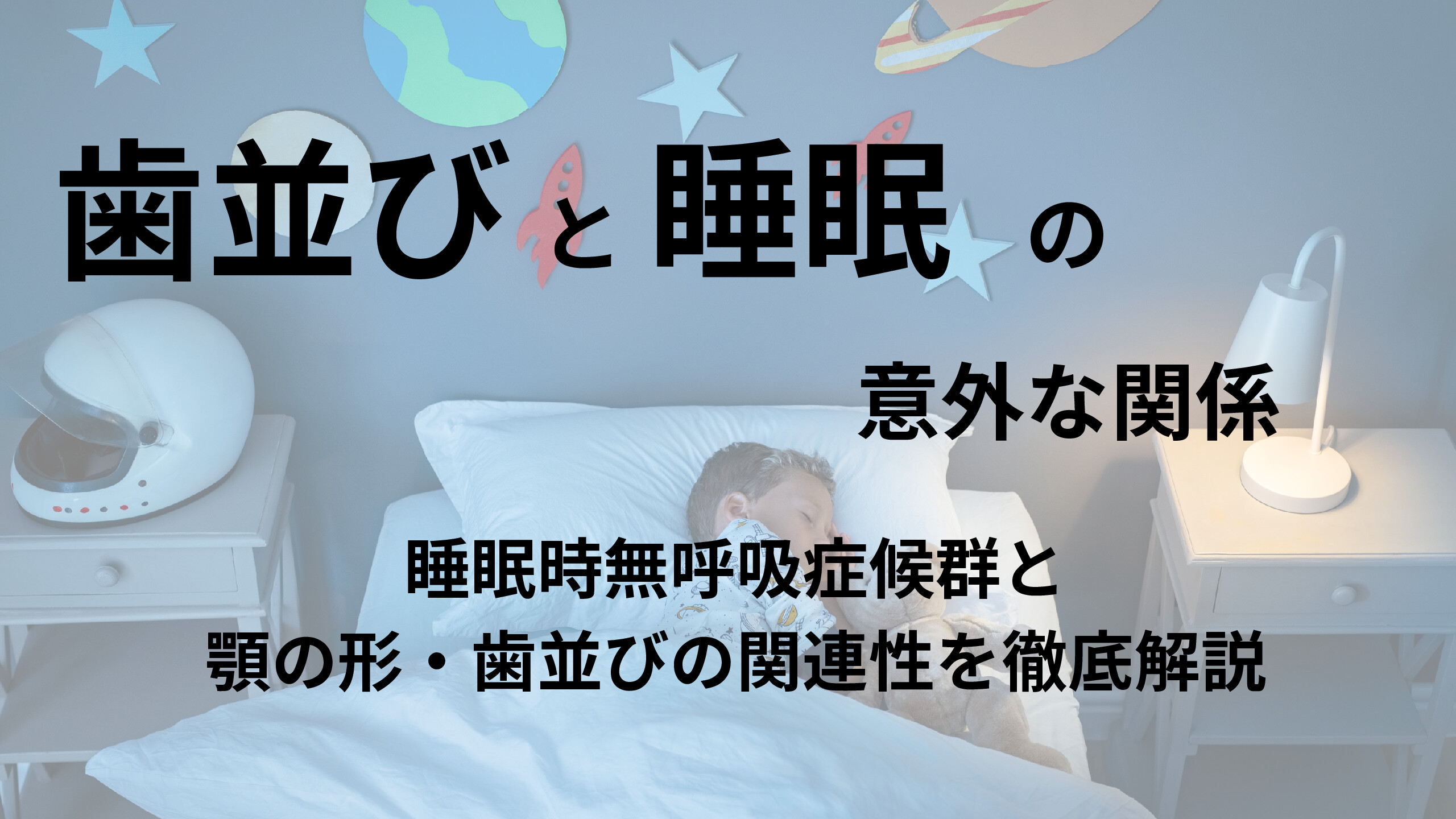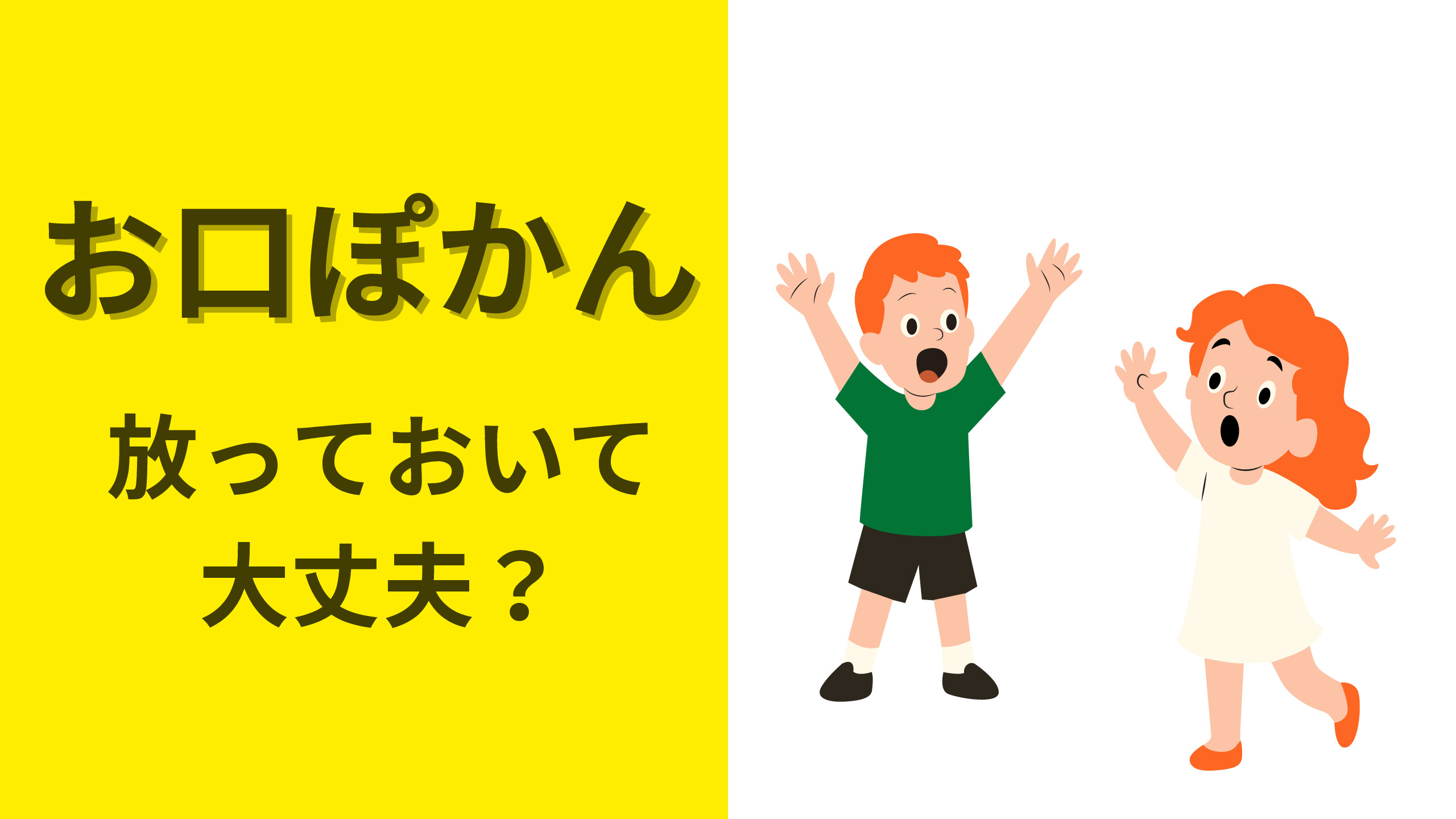お子さんの歯ならびは、遺伝だけでなく「呼吸の仕方」にも大きな影響を受けることをご存じでしょうか?
実は、近年の研究では「口呼吸」と「鼻呼吸」が歯ならびやお顔の発育に大きく関係していることが明らかになっています。今回は、呼吸と歯ならびの関係について、皆さまにお伝えします。
なぜ呼吸と歯ならびが関係するの?
呼吸の方法には大きく分けて「鼻呼吸」と「口呼吸」があります。
• 鼻呼吸:鼻から空気を取り入れる。自然で健康的な呼吸法。
• 口呼吸:口をポカンと開けて、口から空気を取り入れる。習慣化すると問題が起こりやすい。
子どものあごや歯ならびは、成長期に周囲の筋肉(舌・唇・頬の力)のバランスを受けながら発育します。ところが、口呼吸になると舌の位置が下がり、上あごの成長が抑えられ、歯ならびに影響が出てしまうのです。
口呼吸がもたらす歯ならびへの影響
口呼吸が習慣になると、次のような問題が起こりやすくなります。
1. 上あごの横幅が狭くなる
本来、舌は上あごにピタッとついて「天然の矯正装置」のような役割を果たしています。口呼吸だと舌が下がるため、上あごが横に広がらず、歯が並ぶスペースが不足します。
2. 出っ歯や受け口のリスク
唇や頬の筋肉のバランスが崩れ、前歯が出てきたり、かみ合わせが乱れることがあります。
3. 「アデノイド顔貌」になる可能性
鼻づまりや口呼吸を続けると、顔が細長くなり、下あごが後ろに下がった独特の顔つき(アデノイド顔貌)になることがあります。
科学的根拠
複数の研究で、口呼吸と歯ならびの悪化には明確な関連が報告されています。
• 慢性的な口呼吸の子どもは鼻呼吸の子どもに比べて、歯列弓が狭く、開咬や上顎前突といった不正咬合が有意に多い。
• 口呼吸の子どもは鼻呼吸の子どもに比べて上あごの幅が狭く、歯列不正のリスクが高い。
など、医学的に「呼吸の仕方が歯ならびに影響する」ことは裏付けられているのです。
ご家庭で気づけるチェックポイント
お子さんにこんな様子はありませんか?
• 口がいつも開いている
• 寝ているときにいびきをかく
• 朝起きたときに口が乾いている
• 姿勢が猫背気味
• 前歯が出てきている、歯並びがガタガタ
これらが当てはまる場合、口呼吸の習慣があるかもしれません。
口呼吸を改善するためにできること
1. 耳鼻科でのチェック
アデノイド肥大やアレルギー性鼻炎など、鼻づまりの原因がある場合は耳鼻科での治療が必要です。
2. 舌のトレーニング(MFT)
歯科医院では、舌や唇の筋肉を正しく使うためのトレーニング(口腔筋機能療法:MFT)を行います。舌を上あごにつける練習や、口を閉じる力を強くする運動などが効果的です。
3. 矯正治療との併用
必要に応じて、成長期の子どもには顎の発育を助ける矯正装置を使い、歯並びと呼吸の両方を改善していきます。
お母様方へのメッセージ
「歯ならびが悪いのは遺伝だから…」と思っている方も少なくありません。
もちろん遺伝的な要素はありますが、生活習慣、特に「呼吸の仕方」が大きく関係しています。
お子さんの歯ならびをきれいにすることは、見た目だけでなく、将来の健康や集中力、睡眠の質にもつながります。早めに気づき、対処することで、大がかりな矯正治療を避けられることもあります。
まとめ
• 口呼吸は歯ならびの乱れやあごの成長に影響する
• 科学的にも、口呼吸と不正咬合の関連は証明されている
• 鼻づまりや習慣の改善、舌のトレーニング、矯正治療でサポート可能
• ママさんが早めに気づいてあげることが、将来の大きな予防につながる
お子さんの口元や呼吸の癖が気になったら、ぜひお気軽にご相談ください。
⸻
📖 参考文献
• Harari D, Redlich M, Miri S, Hamud T, Gross M. The effect of mouth breathing versus nasal breathing on dentofacial and craniofacial development in orthodontic patients. Laryngoscope. 2010;120(10):2089-2093.
• Souki BQ, Pimenta GB, Souki MQ, Franco LP, Becker HM. Prevalence of malocclusion among mouth breathing children: do expectations meet reality? Int J Pediatr Otorhinolaryngol. 2009;73(5):767-773.
【執筆・監修者】
あいおいこども矯正歯科 院長
村木駿介 (歯科医師)
顎咬合学会会員