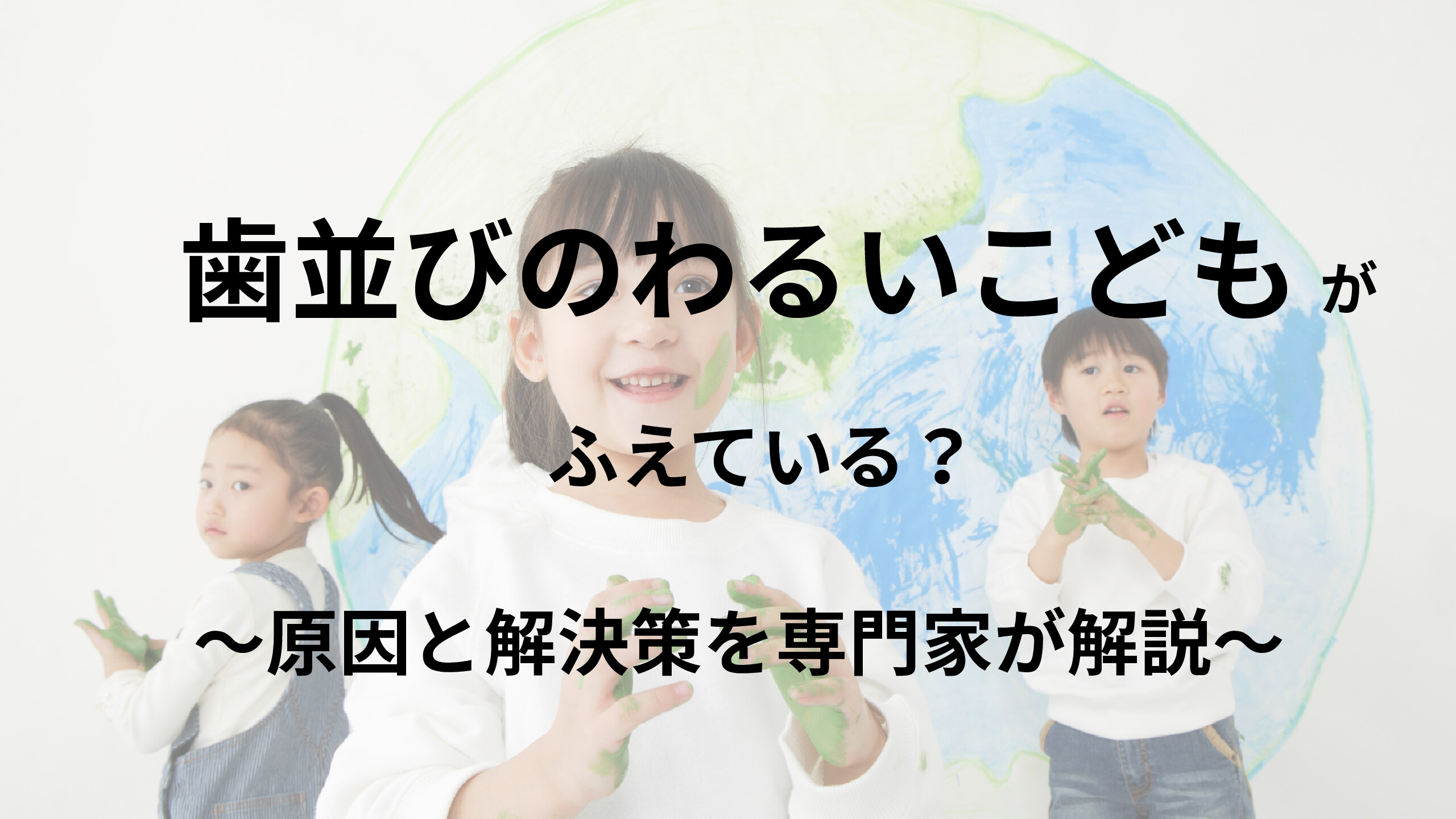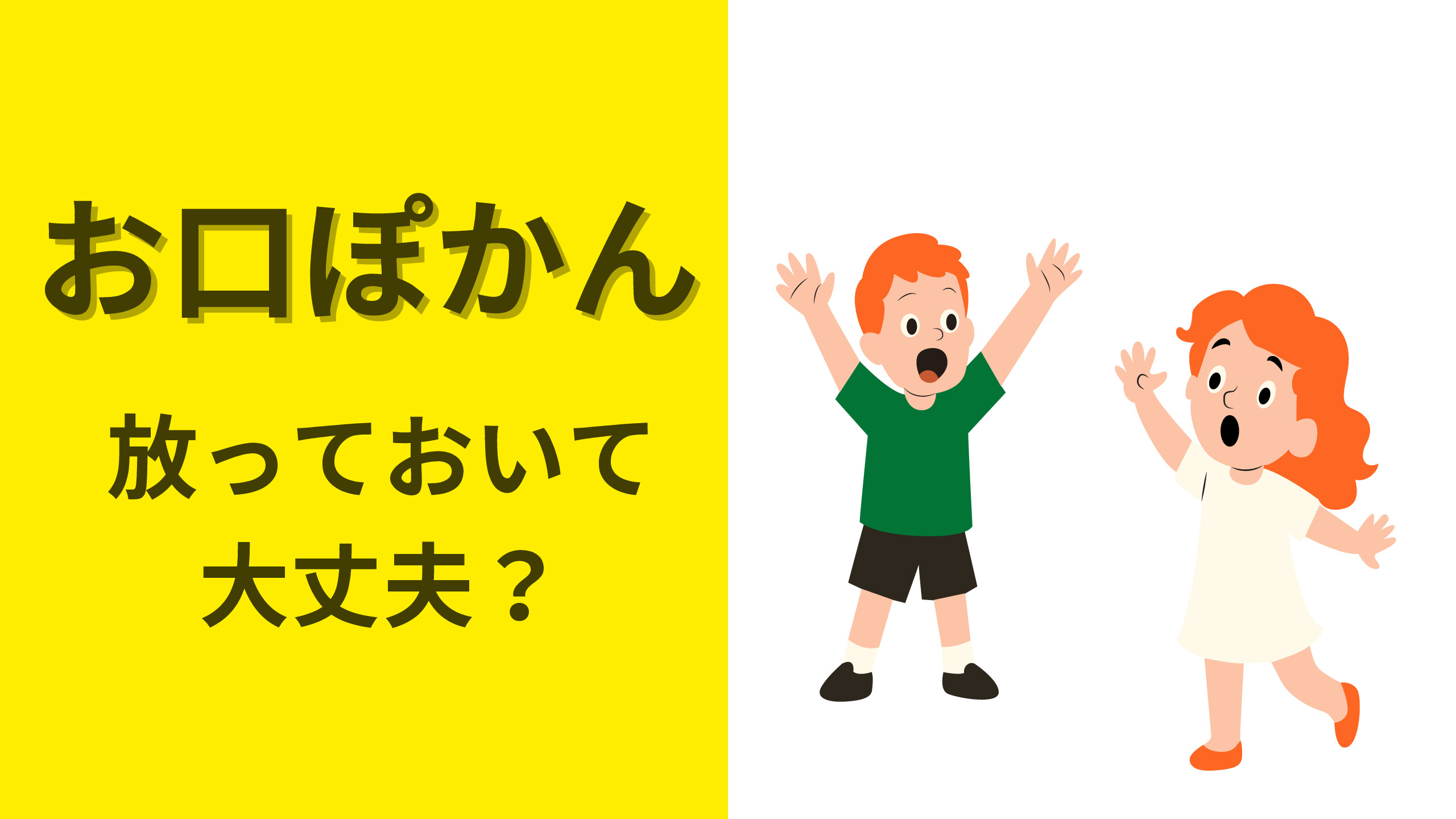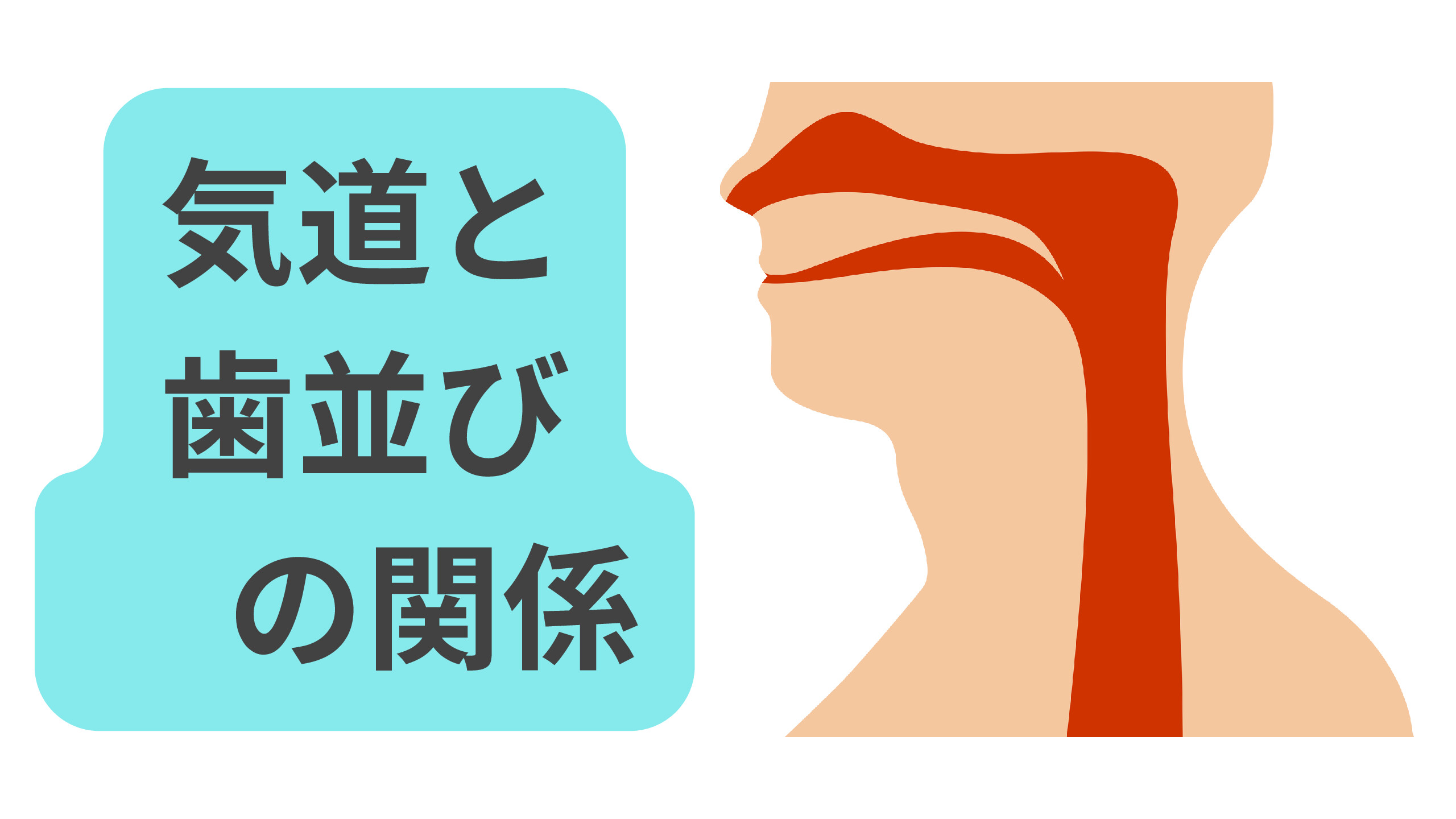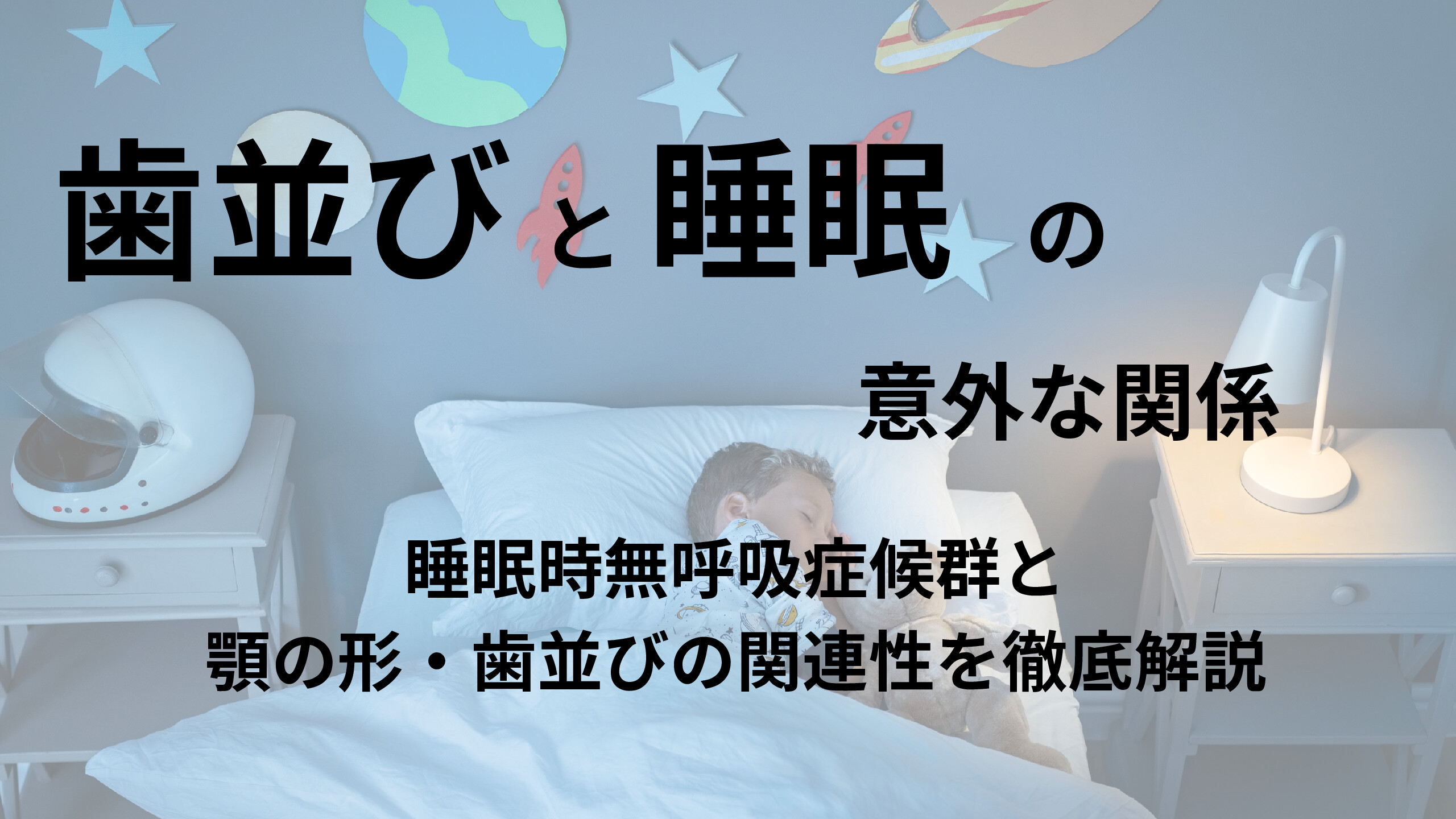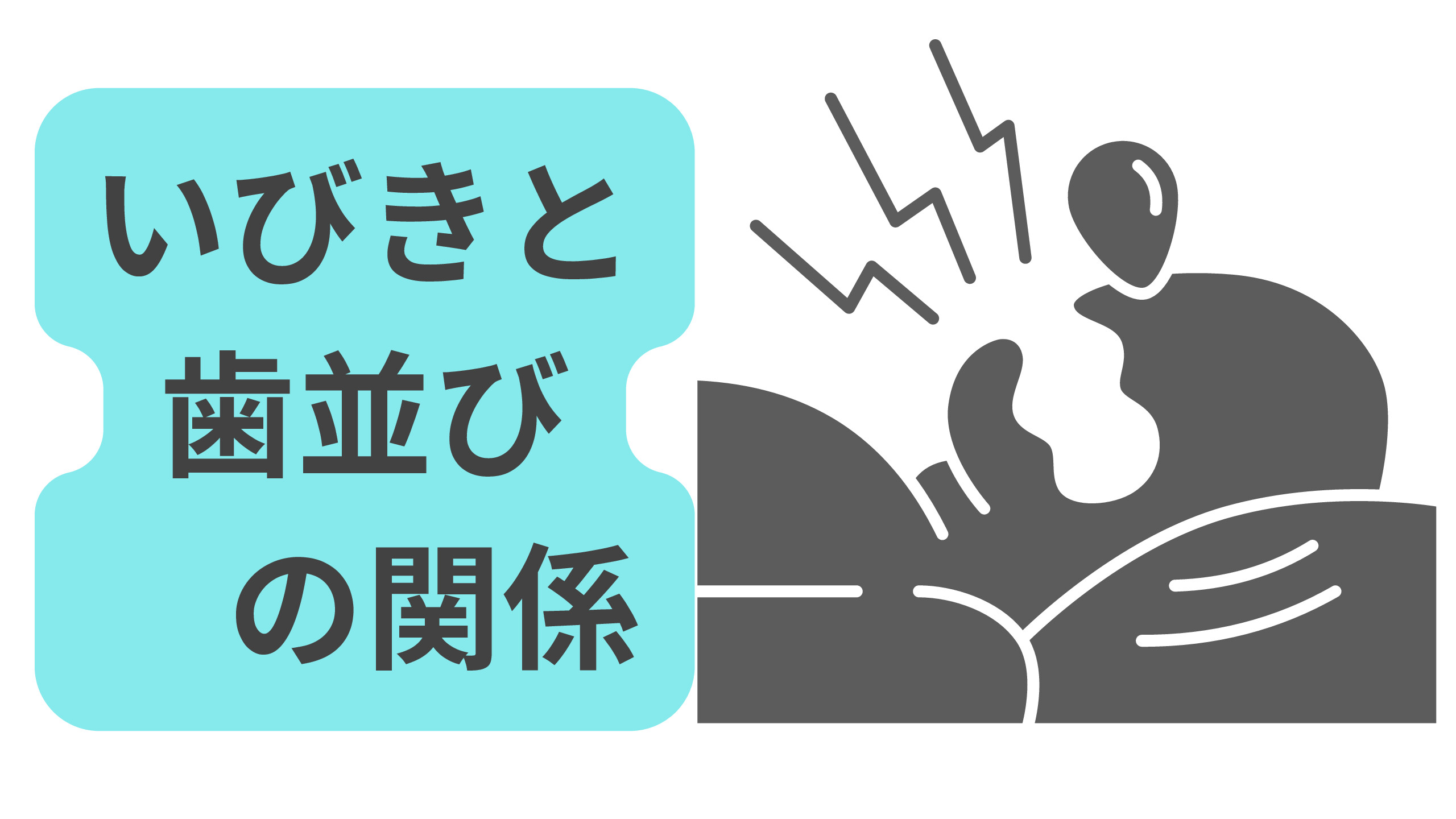「子どもの指しゃぶり、いつまでにやめさせた方がいいですか?」
小さなお子さんを持つ保護者の方から、歯科医院ではよくいただくご相談です。
赤ちゃんにとって指しゃぶりは自然な行動であり、心の安定にもつながります。しかし、長く続くと歯並びや噛み合わせに悪影響を及ぼすことが分かっています。今回は、指しゃぶりは何歳までにやめるべきか、最新のエビデンスをもとに解説します。
指しゃぶりは成長の一部?いつから始まるの?
指しゃぶりは「非栄養的吸啜(ひえいようてききゅうてつ)」と呼ばれ、母乳を吸う動作と同じ反射行動のひとつです。眠いときや不安なときに安心するために行われることが多く、生後数か月から自然に見られるようになります。
多くの場合、2〜3歳までには自然に回数や時間が減少していきます。そのため、幼児期の指しゃぶり自体を過度に心配する必要はありません。
指しゃぶりが長く続くと歯並びに悪影響が
一方で、4歳、5歳を過ぎても続く場合には注意が必要です。
指しゃぶりの力や持続時間が長いほど、歯や顎の発達に影響を及ぼすリスクが高まります。代表的な影響には次のようなものがあります。
- 出っ歯(上顎前突):前歯が前方に傾く
- 開咬(オープンバイト):前歯が噛み合わず隙間ができる
- 交叉咬合(クロスバイト):奥歯の噛み合わせがずれる
- 発音や咀嚼の障害:言葉の発音や食べ方に影響
これらの変化は、永久歯が生え始める時期(5〜6歳以降)には自然改善が難しくなり、将来的に矯正治療が必要になることもあります。
指しゃぶりは何歳までにやめさせるべき?
目安は次の通りです。
- 3歳頃まで→ 自然にやめることが多いため、無理に介入しなくてもよい時期。
- 4歳を過ぎても続く場合→ 歯並びへの影響が出るリスクが高まり、専門的なサポートを検討。
- 5歳まで→ 永久歯が萌出する前のタイミング。5歳までにやめることが強く推奨されています。
アメリカ小児歯科学会(AAPD)のガイドラインやスウェーデンの追跡研究でも、4歳を過ぎると不正咬合の発生率が有意に高まると報告されています。
指しゃぶりをやめさせる方法と家庭でできる工夫
指しゃぶりをやめるサポートは「叱る」よりも「褒める」「安心させる」ことがポイントです。
家庭でできる工夫
- 絵本やイラストで「やめると歯がきれいになる」と伝える
- 就寝時にお気に入りのぬいぐるみを持たせる
- 手袋や指カバーで無意識にしゃぶるのを防ぐ
- 「今日はできたね!」と成功体験を褒める
- 不安や退屈が原因の場合は、安心できる環境をつくる
歯科医院でのサポート
4歳を過ぎても習慣が強い場合は、歯科医院でご相談ください。必要に応じて、簡単な装置やアドバイスで改善をサポートできます。
まとめ:指しゃぶりは「5歳まで」が分かれ目
指しゃぶりは自然な成長過程ですが、3歳を過ぎても続いている場合は少し注意が必要です。
そして、5歳までにやめられないと歯並びや噛み合わせに悪影響が出る可能性もあるため、早めの対応が望まれます。
もし「なかなかやめられない」「歯並びが心配」という場合は、ぜひ一度当院へご相談ください。お子さんの健やかな成長ときれいな歯並びを、一緒にサポートしていきましょう。
参考文献
- American Academy of Pediatric Dentistry (AAPD). Guideline on Acquired Oral Habits.
- Dimberg L, et al. Finger sucking, pacifier use, and dental characteristics in Swedish children. BMC Oral Health. 2014.
- NCBI Bookshelf: Thumb Sucking (2020).
【執筆・監修者】
あいおいこども矯正歯科 院長
村木駿介 (歯科医師)
顎咬合学会会員